【この物語はフィクションです】
教師をしてもう3年が経つ。
もう中学校の流れには慣れてきたし、だいぶと容量もつかんできている。
ただ、それが問題ではない。僕は教師としては最悪の事態を迎えている。それは、生徒が俺の言うことを聞いてくれない、ということだ。
いくら正しいことを言っても見向きもしない。反抗する生徒ばっかりだ。
はじめは真面目でいい子たちだったのに、今では憎くて仕方がない。
そんな不満や愚痴をブツブツ呟きながら居酒屋で飲んでいた。
気づいたら周りにはほとんど人はいなく、店内には俺とその他に店長と数名の客しかいなかった。
「どうしたんですか、さっきからブツブツと。」
店長が声をかける。
「いや、何というか学校でうまくいってなくて、、、」
「といいますと?」
「生徒が言うことを聞いてくれないんです。聞いてくれないというか、僕を嫌っているような気がして。」
「ほう。」
「僕の中では正しいことを言っているつもりなんですけど、生徒はそれを聞く気もしないというか、他の先生だったら話を聞くんですけどね。」
「そうですか。」
「もう何が悪いのかわかんないです。」
しばらくの間を空けて、店長は言った。
「私も実は教師をしたことがありましてね。ただ的確なアドバイスができるかどうかはわかりませんが、何個か質問をしてもいいですか?」
「質問ですか、まあ、いいですよ。」
残っていたビールを一気に飲み干す。
「先生は生徒に注意するとき、どんな気持ちで注意しているんですか?」
「そりゃ、そんなことをしてはいけないぞ、という気持ちですかね。」
「それだけですか?」
「あとは、まあ、なんでそんなことをするんだ、っていう怒りみたいなものもありますが。」
「そうですか。じゃあ質問を変えますね。先生という職は学校の中でどんな立場だと思いますか?」
「もちろん、先生は模範となるべき存在ですし、学校では偉い人でしょう。先生は生徒になめられてはおしまいです。
また、生徒を成長させるには我々がいなければなりません。我々が厳しくしないと、生徒は間違った方向に進んでしまいますから。」
「なるほど、、、」
店長はまたしばらく黙り込んだ。どうやら何か言いたげなそんな顔だった。
「何か言いたいことでも?」
「そうですね、おそらく生徒が先生の言うことを聞かない理由はそこにあると思います。」
「そこって、どこですか、、、?」
「あなたの考えです。聞いていると先生は上、生徒は下、みたいに2者の関係を上下で見ている。
でもそれはおそらく本当のあり方ではないでしょう。」
「ではどういう見方をすればいいんですか??」
思わず声を荒げる。自分の今までの考えをすべて否定されたような気分がした。
「横の関係です。先生は別に偉くなくていいし、体裁を気にする必要もない。
ただ、生徒の成長の後押しをしてあげるサポーターなんだと思います。僕はいつも、力ある脇役と言っています。」
店長はさらに続ける。
「あなたは生徒に接する時、お前は間違っている、俺は正しい、みたいな気持ちで注意したりしていませんか?
もしくは、言うことを聞かそうという意識がどこかにあるのでは?」
しばらく考えてみる。じっくりと今までの自分を振り返ってみると、受け入れたくはないが、そうだという心当たりがある。
「確かにそうかもしれません。」
「そしてもう一つ。
先生って、もしかして生徒にビビっているのではないでしょうか?」
ビビってる?まさかそんなはずはない。なんで僕が生徒にビビらないといけないのか。
「そんなことはないと思います。」
「そうですか。でも生徒になめられてはいけない、と感じているんですよね?
または、先生は模範となるべきだと。私が思うに、あなたは生徒になめられることを恐れている。
模範的な完璧な先生から外れてしまうことを恐れている。そうじゃないですか?」
店長は静かに言い放つ。その小さな言葉は、しかし、自分の心を大きくえぐる、そんな気がした。
「僕が恐れている、、、」
「はい。僕も昔はそうでした。生徒になめられてはいけない。体裁を保たないと、って。
しかし、あるとき気づいたんです。先生ってそんなもんじゃないって。
それから生徒たちの僕に対する程度は変わっていきました。」
今までそんなこと考えたこともなかった。
しかし、店長の言葉は重く自分にのしかかってくるを感じる。それは的を得たものだという意味以外の何ものでもない。
「その恐れが生徒に伝わっている、ということですか。」
「はい、その可能性は十分あると思います。結局注意をするのも、生徒に声かけをするのも、結局自分を守るためにしている行動だからです。
子供とは不思議なもので、そういう細かな違いを感じ取ります。
だから、例え他の先生と同じことを言っていても、先生によって言うことを聞く生徒と、聞かない生徒に分かれるんです。
それを分ける違いは、その行動が先生自身を守るためなのか、生徒のことを思ってしていることなのか、というところでしょう。」
反論の余地はなかった。なぜ今まで気がつかなかったのか。
その自分の鈍感さと、自分に対する恥ずかしさで一杯だった。
「自分が情けない、、、」
「いえ、別に恥じることはありません。それもすべてステップの一つ。
一つ成長していけたならまた前を進めます。生徒も先生も前を歩く、という意味では同じですよ。」
そう言って店長はビールをもう一瓶持ってきれくれた。
「これはサービスです。」
ニコッと笑ってそのあと、他の接客をし始めた。
あともう一瓶だけ飲むか。
明日から新たな毎日がスタートする、そんな気がした。

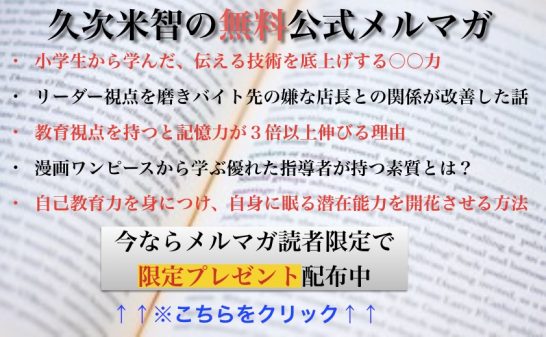














コメントを残す