この記事は前回の続きとなっているので、見ていない方はこちらからどうぞ
承認欲求を求めた先にあるものは、、、
【この物語はフィクションです。】
先輩の言ったことがずっと頭から忘れられない。
自分のエネルギーが足りないから人から奪おうとする。じゃあどうやったらそれを増やせれるのか。
友達と考えていてもどうも答えにたどりつかない。
と思いながら学食でランチを食べていると、先輩の姿が見えた。
「先輩、お久しぶりです!」
「おう、」
「先輩もここでランチを食べるんですね。でも一人なんですか?」
「俺は大概一人で食べるか、昼は食べへん。そんなもんや。」
「そうですか、、、あの〜」
「なんや。」
「この前の続きを教えて欲しいんですけど、、、」
「はっ?それは自分で考えろと言ったやろ。」
「それはそうなんですけど、全然浮かばなくて。」
「そうやってすぐ答えを知ろうとするからあかんねん。
もっと死に物狂いで考えてみろよ。じゃないとお前はこの後ずっと
答えを探し求める人生になるぞ。」
「はい、、、すみません、、」
「まあいい。ここに座れ。」
怖かった。先輩がこんなに言うことなんてそうなかったから、心臓がバクバクだ。
「失礼します。」
「あのな、この世の中には想念というものがたくさんある。それは常識かもしれへんし、
親から聞かされ続けられたものかもしれへんし、自分が勝手に信じ込んでいるものかもしれへん。
ただ、どれにしてもそれらはすべて幻想で、関係ない。」
「想念、、、」
「多くの人がこの想念を信じ込んでしまっているために、本来の能力が発揮されなかったり、
がんじがらめになっている。お前もその一人や。」
「、、、、」
「この前言った、エネルギーがない人は自分で自分のエネルギーをなくしている。
その代わりに他の人からエネルギーを奪う。でも自分で失くしているからまた同じことの繰り返し。
それは半永久的に行われ、変わらない、変われない。」
わけがわからなくなった。
「、、、、僕、、、、どうしたらいいかもう本当にわかんないです。」
「じゃあゆっくり言うで。
人から認められたい、ということは人に自分の価値を認めさせたい、ということ。
そしてそれを他人から奪おうとしているのが承認欲求。
それを考えたら、実は自分がやることなんてめちゃシンプルや。」
ここで何か言わないと、また考えてないと言われそう。
ない頭から絞って答えを出してみる。
「開き直る、、、とか、、ですか、、?」
「んー、悪くはないか。
路線はそんな感じや。もっと言うと、自分の価値はすでにあると知ること。
たったそれだけ。」
「えっ、、、」
自分の価値を信じる、、、自分が価値がある、、、
「そのまんまや。たったそれだけ。
人は自分の存在価値がないと錯覚している。
それはさっき言った想念。でもそんなのはでまかせで、この世の中で価値のないやつなんていない。」
先輩はさらに続けて言う。
「もう生きているだけで価値があるねんて。
なのに、親から条件付きの愛を注がれて、何かができないと自分は価値がないと勘違いしたり、
今まで植え付けられた間違いだらけの想念に縛られてる。
でも、そんなんない。誰かに認められなくたって、絶対価値がある!
それをまずは知ることが大事なんや。それがまずスタート地点。」
先輩の顔は赤くなっていた。
自分は絶対に価値がある。それを知ること。
それは今までの自分になかったものだった。
「こんなこと言ってるけど、俺だって昔そうやってん。
勉強できる自分、スポーツができる自分、親の手伝いができる自分が価値ある存在なんやって。
でも、そんなんちがう。その考えでいる以上、全ての行動基準は他人になる。
他人の評価を気にして、媚び売って、無駄に評価を上げるために何かをする、
それができなかったら、他人を馬鹿にして自分を正当化する、
そんなことの繰り返し。でもそんな人生嫌やろ?
そんなん自分の人生ちゃうやん。他人の人生やん。」
自分が震えているのを感じた。そしてそれと同じくらい先輩も震えていた。
「俺はお前が何かできるから、自分にとって利点があるから一緒にいるんちがう。
お前という存在自体がかけがえのないものやから一緒にいてる。
俺に敬語を使うからでも、
誘ったら飲み会に来てくれるからでも、
家に泊まらしてくれるからでも、
笑いを取れるからでもない。
ただ、お前という素晴らしい存在があるから一緒にいてる。
何もお前から見返りなんて求めてないよ。」
何も言えなかった。
気がついたら服はベチョベチョに濡れていた。
「エネルギーがない人は、本当はあるのに自分で捨ててる。
自分はダメだ、価値がない、何かをしない自分でないと、、、
そんな気持ちがどこかにある。
そして自分で自分を傷つけて、自分の器をつついて
エネルギーがその空いた穴から抜けていっているんや。
もうそんなことしなくていい。そんなことする必要はない。」
先輩も半泣きだった。先輩の一言一言に先輩の魂を感じる。
初めて言われた。
自分は価値がある、何かをしている自分が価値があるんじゃないと。
思えば昔から親に条件付きの愛を注がれていたのかもしれない。
何かができる自分でないと褒めてくれなかった、
愛してくれなかった。
「、、、ありがとう、、ござい、ます、、」
それが言える精一杯の言葉だった。
もう顔はくしゃくしゃに違いない。
「、、、まあ、そんな感じだ。もう泣くな。こんなとこで泣かれたら
俺が悪いことをしたみたいになるやんけ笑」
さっきまで半泣きだった先輩の顔はもう普通になっている。
「そろそろ行くか。」
、、、、、、、、
そのあとはまた昼から授業に出た。
もちろん泣いていることを友達にばれたくなかったから顔を何度も洗ったのは言うまでもない。

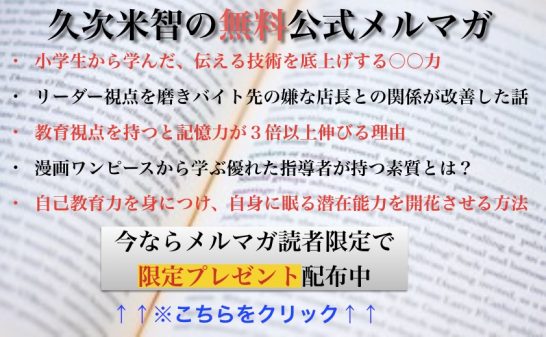














コメントを残す